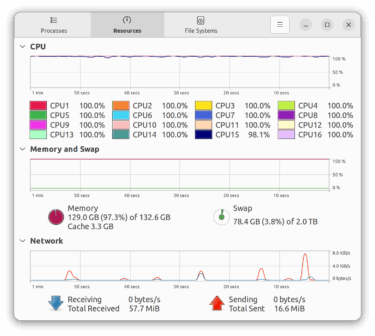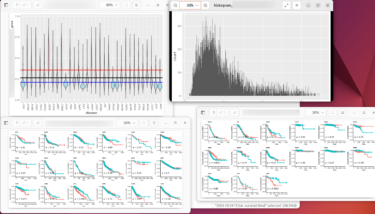日付;2025/10/06(月)
はじめに
2つ目の創薬ベンチャーに転職することにした理由を覚書しておこう思う。特に面白いことを書いているわけではないが、こうやって記録しておかないとどうしても後で忘れてしまう。これは自分が2社目のベンチャーに転職に至った理由を書いたものであり、同時に、創薬ベンチャーが短期間で何らかの成果を残し収益につなげるうえでの実際の落とし穴の一例と考えている。
この会社の人たちは、どのような生活をして、何を食ったらそんなに性格が良くなるのか不思議なくらい良い人達で、そして、みんな賢い人たちだった。社会人として非常に優秀であり、一方、自分の性格の悪さは際立っていたように思う。また、会社のシステムとしてもブラックなところは全くなく、M&A(Marger and Aquisition)後に着任したCEOは、判断力があり、柔軟で、人間的にも非常に優秀な人だった。実際に相当に働きやすい会社に変わったように見える。
これは個人の感想でしかないのだが、その一方で、どうしても何かを研究、開発、実装する能力が高いとは思えなかったことも、残念ながら事実である。感覚的な事を言えば、何かこう、多くの部分でクリティカルではない。おそらくこれに関連していると思うのだが、創業時の開発の効率の悪さが、取り返し出来ない大きな負債に成っているようにも見える。ここからバイオベンチャーとは難しいものであるってことを学ぶことができた。Linkedinで見ながら、数年後にこの会社が本当に大きく成長していることを楽しみにしようと思う。
着任1ヶ月後のM&A
とても驚いたのが、着任1カ月後に急にM&Aされたことだ。これは、自分が就職のための面談を行っている間にもこのような話が進んでいて、さらに、関与しようとするプロジェクトの継続が微妙だったはずなのにそのポジションを募集していたことを示唆している。情報が公開出来ないとは言え、随分と誠実さを欠くように思う。明らかにこれから不安定な方向に向かうとわかっていながら、採用していることになる。金は命より重いって某漫画に書いてあったけど(賭博黙示録カイジ、6巻、219ページ)、これが本当に正しいのであれば、仕事をすることで自分の人生、すなわち命の対価として金をもらうことになるわけであり、ある意味命をかけていると言っても良いはずである。給与は労働力より重い、という感じである。一方、これが誠実に守られない場合は、命よりも重くなり得る給与に関して会社としては今後責任は取らんけど、命すなわち労働力はいただく、ということになり、給与は労働力より重い、という文字通りの意味と反対なことをこの会社はやったことを示唆している。後から耳にした話では、一般的に、世の中にある会社は、その会社がどうなろうとも募集を止めることは無いらしい。その理由は、要はイメージが悪くなって会社の評判に影響し、株価などに影響するためだそう。どうやら、PI(Principal Investigator)などにもこれらを公表していなかったようなので、このような考えで人員の募集も行ってきたのは会社の経営者達ということになる。
一方、当時の自分はと言えば「特に何も変わらずに同じように仕事が出来そうだから、まあいいか」と考えており、これをあまり重視しなかった。しかし、時間が経つにつれて、僅かではあるがプロジェクトや会社の運営等に対しそれが影響しだし、その重要性を理解しだした。2025年になって、これまでBD(Business Development)を行ってきたVP(Vice President)が辞め、次にCMC(Chemistry, Manufacturing and Control)をやっていたVPが辞めた。この時点で、自分は「当初から居るメンバーが見切りを付け出した….」と感じた。これはM&Aで良くあることのようだ。そして、次にM&A以前の前CEOが辞めた。ここで、この会社の活動は一区切り着いてしまったのだと理解し、この時期の会社もしくは前CEOの目的が薬の開発ではなく、会社を売って利益を得ることになっていたことにも気がついた。M&Aを達成させてその1年後、すこし安定してきたようなタイミングで辞任したのだろう。
この時点で、ベンチャーで仕事するにあたって、ベンチャーの目的をしっかり理解しておく必要があると学んだ。それは、薬、モノ、サービス等を創ってそれを売ることに加えて、会社を売ることがバイオベンチャーの目的の一つであり、これが本来の目的である薬、モノ、サービス等を開発することと同じようなウェイトで進行している、ということである。こうなってしまうと、ここでモタモタと時間を使っている暇はない。現状で自分の研究能力は十分なのだから、次の目標に移っても良いと考えた。自分を救うのは自分だけ(賭博黙示録カイジ、1巻、221ページ)である。
研究開発能力
会社が新しくなったわけで、それに応じたシステムになり、その体制で研究開発がスタートしたように見えた。みんな優秀で知識もあるのは明らかな事実である。しかし、何かおかしい。凄く違和感がある。会社の人たちはみんな賢いので、みんな気づいているのではないだろうか。でも、もしそれを実行に移して行動出来ないのであれば、やっぱり何かおかしいのではないだろうか。
やりたいこと・やれること・やるべきこと
以下が何度かミーティングに参加させてもらって生じてしまった疑念である。注釈として、自分が在籍した後半の出来事であり、すでに三ヶ月以上経過しているため、今では大きく変わっている可能性もある。
- この会社は起業してもうすぐ10年経とうとしているのに、なぜこんなにアセットやストラテジーに対しての考えが曖昧なんだろうか。これがもしアカデミアの研究ならば、絶対に論文(成果)にはならないと言える自信がある。
- 会社の強みはどうとか、そういう議論を今になってしている場合なのか。
- もう10年も経つんだから、その強みとやらを使って、目玉商品がいくつか出せていても良いころなのではないだろうか。
- 強みはプラットフォームとか言っているけど、他の会社はさらにその上の桁を行く性能に見えるのだが。
- そのプラットフォームを使って、これまで共同開発を行えた会社はほとんどなかったという結果なんじゃあないだろうか。
- なぜそれが出来ていないのだろうか。
自分はこうやってブロクを運営しており、言うても随分と微弱な収益しか得ていないような奴なので、そんなに強くは言えないが、そんな場合でも収益を考え出した場合に真っ先に考えるのは、イノベーションのジレンマ著者のクレイトン・M・クリステンセンらが彼らの本で述べているような「これまでに解決することが出来なかったユーザーの用事をさっさと片付けることが出来るプロダクトやサービス」を提供するべき、ということだ。それが出来なければ、モノ、サービス、薬でも何でも、利益を得ることは難しいと思う。共同研究・共同開発先を見つけるためには、標的にしている会社のニーズに答えなければならないように思う。そして、それがあまりにも難航するのであれば、間接的ではあるが、それは結果としてニーズを満たせていないということを示唆していると思う。大金も動くし、多くの時間も必要だし。多大な労働力も動くことからも、共同研究・共同開発先を見つけるのは難しいことは理解しているつもりだし、M&Aを経ていることからも自分たちの強みについての議論を改めて行っているのかも知れないが、今更会社の強みはどうとか、他社との差別化が…とかそういう議論を今更しているのは、どうなんだろうか。こうなっている原因は、これまでに作ってきたものが、残念ながら、自分たちが所属する分野や共同研究先のニーズをどれも満たしていない、ということと思うのだが。そして、業績の獲得を加速するならば、強みを活かして云々ではなく(その強みとやらでこれまで十分な成果がないわけだから)、その所属する社会や、最悪の場合共同研究先のニーズを満たすこと(こうなると創薬やモダリティーの開発というか、もはやCROのような業態になるはず。なので、「最悪」という言葉を用いた。利益が第一目標ならば、そうする必要があると思う。)が、これからやるべき事だと思うのだが。
創業者である前CEOや当初からいるVP達が辞めてしまったから、本当に「新しい会社としてスタートしよう」ということで、こういう考えになっているのだろうか。百歩譲ってこれを良しとして、新しい会社と見なした場合を考えてみても、さらに発展させていくために必要なことが検討出来ているだろうか。自分らの居る分野の現状を検討し、必要なことが見えてきたのであれば、やはりそれを真摯に受け止めて、改善するところは改善し、捨てるものはさっさと捨てて、次を考えるべきではないのだろうか。そのトレンドや他社と競うために必要な技術、リソース、人手が足りない場合、以前と同じようなうまく行っていなかった(だからこそM&Aで生きながらえたとも言えると思う)手法で開発を続けるのはどうなんだろうか。最近ではこれらの補充も検討され出したようだが、今から競合に合わせるような形で補充しても、さらに強力な技術やリソースと多くの人手を既に持っている他社と競えるのだろうか。他社は人でもリソースも十倍くらいあるんじゃあないのだろうか。それに今から追い越せるのだろうか。
自分には「わたしたちはこんな技術を持っていますよ!だから、誰か何か買いませんか??」と、すなわち、「すごいと思っているのは自分だけ」の商品を「不特定の誰かに」売ろうとしているように見える。大企業は自分のところでもそんなことは出来るし、より強力なリソースを持っている会社は他にある。まるで「見ているひとは見ていてくれているから、良いものを作れば必ず買ってくれる。」とでも言っているように見える。インダストリーなので、どんな形であれ最終的には利益が必要であり、やるべきことは「ニーズの満たされていない疾患や標的を、その自分たちの強みを使って解決し、共同研究したいならばそのようなことに関心を持っている会社と手を組むこと」が必要なのではないだろうか。
M&Aされて100%子会社化したからこういう活動に舵を切れないのだろうか。だとしたら、親会社はどう考えているのだろうか。このままずっと大きな共同研究なり共同開発に持ち込めず、利益を得ることが出来なくてもいいのだろうか。以降数年で利益が出ない場合は、どうするのだろうか。
普通の白飯しか出していないレストランに、金出すか?レストランに行く客だだって目的はある。そして、このまま運営を続けた場合、まぁ、なんかあるよね。
自分たちの強み・社会が求めていること
自分は会社の運営なんてやったことないし、そもそも研究者だからこういうことは考える必要がない可能性はあるのだが、やはり、今後どうやって給与を上げていくか、とか、どうやったら「面白くなりそうなことに繋がるか」とか、そういうことを考える上では、以下はやっぱり重要であると思う。
- これまでに解決することが出来なかったユーザーの要求を満たすことが出来るプロダクトやサービス(上述の通り)
- ニーズの満たされていない疾患や標的を、その自分たちの強みを使って解決する。共同研究したいならばそのようなことに関心を持っている会社と手を組むこと
薬や治療の開発に携わる研究者が社会貢献しようと思うと、明らかに2番目が重要と思いたい。そして、自分の強みを使うのは良いが、目的を特定し、それをしっかりと固定して標的を定め、それを解決するために必要な、合理的な手段で仕事を進める必要があると思う。
化合物が薬であるためには、何かの疾患を治療したり、何か有益な作用をもたらす必要がある。だから、目標をしっかりと固定するためには、その標的を医学的な観点から考える必要がある。それには医者を味方につけるのが最短である。そのためにKey Opionion Leaderとか言う企業イキリ用語が存在するのだと思っていたのだが….彼らはそのような用語を何のために使っているのだろうか、自分のPresense(企業イキり用語の一つ。それこそ、周囲に対してイキっていることを示す用語。)を示したいだけなのだろうか。それが出来ない場合、当然自分たちで調査しなければならない。そして、昨今ではTCGAやCPTACなど、公的なデータベースだって利用できるので、そのようなニーズや標的を科学的に見つけることも十分に可能と考えている。それなのに、何故かそれをやらない。「大手企業もやっている」というコメントを受けたことがあるが、それは、やらなければニーズを見つけることが出来ないので当然やっているのだと思う。その上でKey Opinion Leaderにアプローチするのではないのだろうか。「大手企業もやっていることを自分たちがやっても仕方ない」と考えるのは違うと思う。大学受験で「数学はみんなやってるから、自分たちはやらない」と言っているようなものである。共通として必須なんだから、やる必要がある。
また、なぜ既存の良い薬があるのに、それの「改良品」みたいなモノを開発しようとするのだろうか。これも使う側のことを考えてみれば良い。もう散々臨床研究もされて、薬効も十分に証明されている薬である。モダリティーを変えてしまうのだから、薬効も副作用も治療成績も変わってくるはずであり、それは現状の治療に必要なものではない。モダリティーを変えるのであれば、それこそ、既存の良い薬よりもその性能を相当に上回る開発品を作る必要がある。
別の観点から考えてみると、他の問題もあると思う。自分たちの「強み」を活かす場合、その分野の慣用的な開発しか出来ないのだろうか。ここで、研究者にありがちな行動が連想されてしまう。「自分たちの強み」を悪く解釈すると、それは「趣味」になってしまうように思う。また、もし他社の勢いが強くなれば、こっちが真似事になってしまい、もうそれは、「強み」と言えるのだろうか。こういった状況になって「自分の強み」を活かして創薬しようという意気込みは理解出来たものの、まるで魚のいない川で釣れない餌を頑張って投げているように見えた。ニーズを捉える解析を全く行っていないし、公開データベースを用いた解析は自分だけでなく大手企業も同様に行うことが出来るという理由から、今後も本腰を入れる疾患の解析を行う気はないらしかった。上述のように、医学的なニーズや未解決な部分を世の中のツールを使ってなんとかして探し、それを自分たちの強みを使って解決しなくてはならない。ミーティングを聞いていて、なぜ良い薬が既に出ているようなものを作ってしまうのだろう。求められているものは何か、考えているのだろうか。これこそが大手企業が着目している化合物ではないのか。M&Aや創業者の性質を見ていても、実はここはケミストの趣味をやる会社、つまり、やっていることはこのブログと同じレベルな気がして仕方なかった。本当に必要とされているものに着目し、それを開発なり実装したらどうなんだろうか。
サンクコスト
言うても、上記の研究開発や需要のある標的を見つけることは、考え方次第で如何ようにも出来るように思う。元々開発能力は非常に高いのだから、あとは戦略と解析能力次第であるはず。
しかし、どうしても理解できなかったことがある。これは自分が感じたことであり、会社としてはそのように考えていないかも知れなが、自分には、とあるプロジェクトが圧倒的なサンクコスト(Sunk cost)を持つように思えた。推測だが、ある開発品で大手企業との共同開発に結びつけることが出来なかったため、会社はM&Aに舵を切ったのだと思う。確かに、この化合物の作用機序は面白く、かなり有望であると思う。とある分野ではちょうどホワイトスペースを付いたような作用機序であると思う。だからこそ、最初は投資してもらえたのだろう。うまいことすれば、これまでのようにベンチャーキャピタルからも資金を得ることが出来ると、今でも本当に思っているし、そうするためには何を出せば良いか理解出来ているし、実現する自信もある。しかし、詳しいことは都合上言えないが、自分にはこの化合物は推定されるMOA(Mechanisms of Action; 作用機序)もPOC(Proof of concept; 概念実証)も検証、実証されていないように見えた。今は既に立ち返る時間は無く、それに資金を費やすことも出来ないことになってしまっているように見えた。最初から適切で効率的な研究を行っていれば、これは完全に避けることが出来たと確信している。本当に勿体ないことだ。今後、この成果についてはLinkedinで見させてもらおうと思う。
この結果は、このプロジェクトを主導してきたリーダーの能力が、残念ながら不足していることを示唆している。そして、日頃見ていると、少なくともこれまでは結果として基礎研究を舐めてきたのではないだろうか。in vitroではどんな細胞株もしくはどの組織由来の細胞を、何種類使えば信頼できる結論を得ることが出来るのかなど、真っ当な大学では教わることである。知らなくても、これは既にCancer ResearchのAuther Guideにも書いてあったし、もしかしたら今はもっと厳しいかもしれない。どういう理由からなのかは知る由もないが、このリーダーはそれ知らない、もしくは無視していると言える。なぜ無視して良いと思ったのだろうか。アカデミアじゃあないからとか、時間がないからと言って無視すると、上記のような結果が待っているので避けて通るのは不可能であり、もし上手く行ったとしてもそれはたまたまギャンブルに勝っただけである。それに加えて、過去の重要な分岐点や企業イキり用語で言うところのDesicionが間違っていたことを示している。その標的が発現する細胞は何か、その標的は生体内や標的疾患でどのような役割を担っているのか、どのような細胞株や細胞をモデルとしてリード最適化に使用しなければならないのか等、明らかに計画が良くない。それにも関わらず実行、継続して、サンクコストとみなす事が出来るまでに長年やってしまった理由としては、それを実現する方法を知らなかったり、その意欲がなかったり、面倒臭がって楽な方に逃げたり、実験結果を正直に正しく解釈できなかったり、その結果を受けて計画を正しく修正しなかったりしたことが考えられる。実際、このリーダーからは「逃げ切る」という発言が、片手で数えるには少なすぎるくらい有った。高齢であることもあり、これは本音なんだろう。明らかに最悪である。おそらく、彼女はリーダーとしての知識、能力、責任感、やる気、マネージメント能力など、どれをとっても不足している。こんなことに成ってしまった理由のほとんどは彼女にあると言って良い。傍から見れば、誰がどう見てもそうなると思う。彼女が会社に与えた損害は甚大であると考えている。こうなってくると、その上のリーダーにも問題がある。こんなに薬効が無い開発品なんだから、なぜ「何かがおかしい」と最初に考えなかったのだろうか。自分は、これには複数の要因が絡んでいると思っている。先ずは上述したように、医学研究を舐めていることがある。適切なモデルを選んで居なかったりするあたりは正にその証拠であり、自分がミーティングでの発言から感じ取ったことでもある。ケミストかビシネスデベロップメントか知らんけど、結局のところアウトプットは医学であるので、医学の研究開発をするべきである。それを軽んじるリーダーシップであることを示している。
これは製薬ベンチャーの欠点であり、他の会社でも常に気をつけていないと起こり得ることなんじゃあないだろうか。考える余裕がなくなったり、ベンチャーなのに軌道修正が出来なくなっていたり、そもそも、その分野でそのモダリティーを開発を続けていくための能力が備わっていなかったり、色々な理由がこの背景にはあるだろうが、結局のところ、所詮その問題を解決できなかった会社、という結論になってしまう。それが現行しているのであれば、さらに悪い方向に向かうはずである。自分としては、このような会社で、近い将来失敗するだろうプロジェクトに大きな労力を費やすのは、もう止めたほうが良いと判断した次第である。
リーダー
前の職場からそうだったのだか、彼ら彼女らは目的の達成に向けて進んでいるように見えなかった。目的があるならば、それに向かって効率よく進んだり、趣味と成果につなげるべき仕事を分けて考えるるはずだ。前職と異なる所として、この職場では研究開発の効率の悪さが感じられた。結果として、こんなペースでは仕事が出来ない状態になる。
自分は研究員として、実際の研究や解析を行い、良いデータを得て、それを成果につなげたい。どちらの場合でも、どうしても、とあるPIがそれを妨げているとの結論に至った。ある一定の成果を得ていないPIは、少なくとも、研究を成果までまとめる・持って行く能力(研究能力とは別)(はっきり言って日本にはこれは無いと思う)が不足しており、それに加えて、研究能力(目的を理解し、それを達成するための効率的な研究計画、得られたデータの解釈など)、経験(計画、実験、解釈時の落とし穴、一般的なこと)、体力(人に依るが、年齢との関係は深い)、責任感(必ず成果を得る、失敗は最小限に留める必要があるという考え)、マネージメント能力(データの整理、仕事の丸投げなど。これが出来ない奴はおそらく部下をCROか何かだと思って非常に雑に扱う)などが不十分と思う。アカデミアでこんなPIは最悪(でも、かなり多いと思う。だから、日本の科学は、一部を除き、他の先進国と比べてもレベルがだいぶ低い)だが、もしかしたら企業、特にベンチャーは更にひどいように思う。ベンチャーでは、研究能力、経験、体力、責任感、マネージメント能力が一般的に劣る技術員が、技術員ゆえの腰巾着能力の高さ(そもそも、技術員に正しい判断や研究開発の方向性を決めるほどの能力はなく、有益なデシジョンなどは、百歩譲っても自力は出来ない。こういう奴に権限を譲渡するといずれ終わる。指示に従うことしか出来ないと考えても良い)と、創業時から一緒にやっているという、まるで家族経営のような特権だけで、PIに相当するポジションに付いてしまうということがある。技術員上がりの無能リーダーで一番厄介なのは、責任感が無いことだと自分は思う。責任感がないので、明らかに間抜けな計画の実験を部下にやらせて失敗するわけだが、何が失敗の原因だったのかは考えずに、そのデータを無かったことにする。このリーダーは、見せるだけマシだったかも知れない。ただし、後になって実は随分前に同じような実験を行って似たようなネガティブデータを取っていたということが多かった。そして、成功するまで変な実験を繰り返す。様々な観点からデータを解釈出来ず、結果として会社にとって都合の良いように捏造のようなストーリーを組み立てだす。データの解釈や後々に再現性や一貫性に影響するだろう点を指摘すれば、なんだかんだとよくわからない言い訳をして、さらに高齢であることを上手いこと使って言い逃れる。能力も責任感も欠如しており、失敗が約束されている、まるで捏造するための実験計画で、次の実験を行うことになる。そんな物は当然失敗するが、彼女は責任を取ることもなく、ほしい結果が出るまで似たような実験を始める。こういったことに費やした金額が、いちいち高額で、多いときには300万円以上だったりする。ミーティングでは、計画が悪すぎる故のゴミのような結果を示し、何か意味のわからないことを喋って周囲の参加者を煙に巻いていた。ミーティングの参加者(別のチームの者)は困惑しており、呆れ返っていた。しっかりと指摘してやってくれと別チームの者に頼んだくらいだ。2025年9月の時点で実際起こっていることである。ところが、そういう状態とわかっているのに誰も指摘できず(当然、この者以上のポジションでなければそんなことは言えない)、家族経営(どちらかと言えば創業者経営というところか)に近いことや日本では簡単に解雇出来ないこともあり、彼女は2025年9月の時点でもそのプロジェクトを続けている。このプロジェクトは創業のきっかけにも成っている開発品であり、すなわち、その会社が最初に売り出そうとする開発品なわけで、もしこういうリーダーが最初に売り出そうとする開発品を主導する羽目になったら、このリーダーはおそらく数年以内にプロジェクトだけでなく会社も潰し得る。他社のデューデリジェンスで排除されるのはこのためである(自分だったら絶対に買わない)。ベンチャーに限らず、大企業でも、おそらく優秀な人間の腰巾着が出世するのだろうから、こういう人間は多いのかもしれない。そして、社長も、目的の一つが会社を売ることだったりするので、失敗しそうならばその会社をなんとかして売り払ってしまえば、社長の目的は達成される、というストーリーである。すなわち、この間抜けで無能なリーダーが最初の開発品に関して後戻り出来ないほど上手くいっていなくても、VCからなんとか資金を得ることが出来て経営が回っていて、最終的に売りに出されればそれで良いので、こういうリーダーが放置されてしまうのだろう。
ついでに言っておくと、このリーダーは自分の出来ることはやるが、他のことは全部後回しにしていたのではないだろうか。だからこっちの仕事をしっかりと確認することが無かったし、あってもかなり遅かった。
アメリカで研究を行い、日本に帰国してアカデミアとインダストリーで研究活動を行ってみて、こうなってしまうのは「リーダーが原因」であると気がついた。基本的に部下はリーダーに従う必要があり、意見は言えるが、決定件は乏しいためだ。非常に面白い将来的にも明らかに有望な作用機序の開発品でも、このようなリーダーにより、全部潰されてしまう。さらに、有望なプロジェクトに加えて、彼ら彼女らに着いた部下のキャリアも潰しかねない。
少しでも上のポジションに行くことで、こういった間抜けな無能にゴミのようなサイエンスや研究をさせないようにし、自分の関与した有望なモダリティーを無駄に潰すようなことはしないようにしたい。とにかく、無能が偉そうに上に座って、優秀は人材を食いつぶすのは阻止したい。ベンチャーだから、有能な開発品で起こりやすい。しかし、一方で会社の目的の一つが、M&Aだから、別に化合物が売れる必要なない。そこで利益を得るのは社長だけであり、もう詐欺みないなもんである。色々と調べてみると、アメリカのベンチャーなんか、上手くいかない場合は2年くらいで潰れるらしい。日本も、そのくらいドライに会社を潰した方が良いのではないだろうか。駄目な企業や研究室のラボがゴミを出して放置するのは、良くないと思う。投資家としても長年やって回収できなかったのでは、面白くないのではないだろうか。
ついでに言っておくが、社会人枠で卒業した論文博士も、ゴミだからな。なぜ医者の論文博士はそれでも良いのかと言えば、彼らは医療行為を行うことが出来、そのなかで出された論文も非常に有益な研究であることが多く、そして基本的に賢く、今後も医者として社会に必要だからである。医者でもない一般人の論文博士と一緒に考えることは出来ない。そして、なぜ課程博士と同レベルではないのかと言えば、課程博士は自分の研究だけでなく、学生の教育、TA(Teaching Assistant)、ラボの雑用、論文抄読会もこなし、場合に依っては教授からシバかれてきている場合が多く、それらの能力も備わるからだ。社会人の論文博士は、ラボのテーマとは全然関係ないような論文や、逆に会社のテーマとは全然関係ないような論文でゴミのような論文を、ゆっくりと時間をかけて作成し、ゴミのような出版社を使って出版し、医学部であればあのクソ長いだけの博士論文(Doctor Thesis)を書いておらず(医師以外の医学博士もいることに注意。一昔前ならば彼ら彼女らは医科学修士とか医科学博士とか言ったんだが、最近は医学博士とイキって書く輩も多い)、教授数人からの口頭試問なども経験していない(これはちょっと定かではない。でも見たこと無い。社会人の論文博士もこのような口頭試問があるのかわからない。)ためである。
アメリカに居たときに「PIになって無能を思いっきいり切り捨てるのが目的の一つ」といっているポスドクが居たが、今になってその気持ちが本当に良くわかる。彼は元気にしているだろうか。今では自分が「それは必要なんだな」と感じている。このようなリーダーにでもなろうものなら、間違いなく大損害をもたらすと確信している。
リーダーに関してもう一点、腑に落ちないことがある。なぜ業績が十分ではないのに、あんなに高い給与をもらっているのだろうか。そしてそれよりも下位のポジションの部下達は、明らかにこの会社にとってのエッセンシャルワーカーであるのに、なぜこんなにもらっていないのだろうか。給料はあなたの価値なのか 賃金と経済にまつわる神話を解く(ジェイク・ローゼンフィールド、みすず書房)という本に書かれている問題の実例に見えた。
自分のキャリアに不足していることを得るため
上記で、プロジェクトが火の車になっているのはおそらくリーダーが原因(そもそも、創業当時から正しい実験材料を用いて、正しい実験系を使って、正当にデータを評価しフィードバックできて、それを改善出来れいれば、絶対にこんなことにならなかったと思う)であり、かつそれを排除することない会社や、近い将来失敗するだろうプロジェクトに使う時間も労力も無駄である、ということを書いたが、別の転職理由もある。今後さらに給与を上げる(綺麗な言い方としてはキャリアアップ)ためには、マネージメントの必要性もかなり強く感じるためだ。
個人的には、研究をずっとやりたいと考えている。しかし、研究だけをやっていると、給与の水準があるレベルで落ち着いてしまうようだ。自分はアカデミアを去った理由は「自分の研究能力を金に変える必要がある」である。そして、最近では、上述のように、管理できる立場でなければ、非常に有望で有益な開発品を社会に出すことは出来ない。それに、このようなリーダーに有望な開発品を任せるくらいなら、そんな奴は排除したい、と本気で思っている。自分の年齢を考えてみても、このあたりで管理職の経験を積んでおく必要を強く感じている。
また、大手企業のあの「ジョブ型雇用」という体制も色々と考えてしまう。どうも最近はそれが流行りなのか知らないが、そういう大手企業が多い。研究がやりたいからという理由で大手企業の研究職に「ジョブ型雇用」なんかで雇われようものならば、ずっと技術員のような仕事になるはずであり、一生管理できるような給与の高いポジションには付けないのではないかと感じる。大手企業から来た優秀なリーダーに聞いてみたところによると、そういうことは無いらしい。研究職のまま、ポジションが高くなる人も居るようだ。しかし、それは本当だろうか。55歳になって研究職の上位のポジションにいる人の主な仕事は、実際の研究や解析ではなく、どの分野でも統括になるのではないだろうか。給与アップを狙ったり、逆にM&Aで会社を去る必要が生じたために転職しようとしても、マネージメントがない場合はそれより上のレベルは狙うことが出来ず、似たような仕事に着いたけど給与が200万円下がる羽目になると思う。逆に、マネージメント関連の仕事で良い業績があれば、給与アップを狙うことも可能と考えている。
次のキャリアを考えないと詰むかも
だからといって、マネージメントだけをやっていても、それこそ55歳になったときに無能リーダーに成ってしまうようにも思う。自分のこれまで蓄えてきた知識や技術を固定させ、開発品の種類が変わっても再現性がある業績を得ることが出来るように、ある程度の幅を持たせた上で自分の職務経歴書を発展させることを考えている。そのためには、常に自分のスキルや業績の状態を監視しておかなくてはならない。
ベンチャーなので、社会活動が可能な期間は長くはないと考えるべきである。なので、先ずは組織の目標を達成させて、それを次の職務経歴書の一つの柱にしようと考えている。言うてマネージメントのポジションなので、組織の大きな目標が達成されれば、次の職場では、それを再現する必要性がある会社の、さらに良いポジションに応募すれば良いと考えている。もう一つ考えていることは、特にバイオインフォマティクス系の解析技術をしっかりと頭に固定して、より汎用的に使えるような形まで整えておくことを考えている。自分の技術的な取り柄としては、バイオインフォマティクスは考えておくべきである。さまざまな解析手法を用いて非臨床研究を実施、マネージメントし、臨床研究のアプライまで効率よく運用できます、のように捉えておこうと思う。
ただし、これから5年後に目先の目標を達成し、その次も今よりも良いポジションで同等の業務できるとして、その次、すなわち、10年後もしくは、その次のポジションではどうするか、である。それこそ55歳くらいになったときの働き方である。はやり、マネージメントでも技術でもそうだが、時代が求める尖った最新技術が必要になるだろうから、それをしっかりと見据える必要がある。そうしないと、絶対に詰む気がする。それに、60歳になったときに同じような仕事につけるとも到底思えない。会社でも起こすか、60歳以上でもまかり通る仕事が出来るように今から準備をしておく必要もありそう。
最初に感じたことは大概当たる
このポストを見返してみるとこの会社の第一印象として「学術的な能力と経験値が低く、実験計画が無理やりであること」が書いてある。前の職場でも着任前に「ここは****スの開発を行う研究所なんだから、腫瘍の基礎研究はどうなんだろうか….」と思っていた。そして、大部分の予想が当たっていたように感じる。もしかしたら入社前の会社の第一印象はほとんどが正解である可能性がある。これは、転職サイトの口コミや、面談のときに取締役やその他の役員と話をして感じたこと、例えば、この社長、めちゃくちゃ人相悪いな…とか、この社長こんなに興味なさそうなんだ…等も含めてである。これが正しいのであれば、次の職場でも大体は思った通りになるはずである。おそらく「現時点で持っているアセットは最強で、臨床試験まで進むことは出来るだろうが、次世代の開発品を今からでも考えないとそこで詰む」ような気がする。これは経験こその直感なのか、それとも、これは自分「ここまで」と潜在的に決めているからこの通りのことが起こるのだろうか。この予感はどれだけ当たるか、楽しみである。
まとめ
会社の研究開発の効率が悪いように思えてならなかった。なんとか介入しようとしても、ベンチャーのくせに別プロジェクトということで十分に関与出来なかったり(もしくは結果として信頼されていなかったということ)、周りと能力が合っていなかったり(わざわざ低レベルに合わせるつもりも無かった。だって、それによってこっちのレベルが低くなるわけだから。これだから信頼されなかったのかも知れないが、それにより手を動かせば解決出来るかも知れないことに対して5年も10年も費やしたり、結局諦めたりするのは間抜けと感じた)、会社自体にそのような基礎知識がなかった(ベンチャーのクセに腰重すぎじゃあないだろうか)りで、それが全く活きて来なかった。
どう考えても、目的を達成するための手段が不十分に見えた。in vivoはもちろんのこと、in vitroでのPOC(Proof of Concept)さえもしっかりと証明出来ていないじゃあないか。このリーダーの能力は大丈夫だろうか。高齢であることを抜きにしても、これではどう考えても足りていないじゃあないか。会社としてもなぜこんな多くの失敗や損失を許すのだろうか。
創業後から10年近く経過しているのに「自分たちの強みは….」とか言っているところも、ずれている気がした。その強みとやらを活かして、既に収益を得る段階であるべきなんじゃあないのか。強みについて改めて議論するのは許すとして、収益を得る必要があるんだから、その上のレベルでそれを考えてくれ。どの疾患のどの分子を標的にするべきなのか、なぜ解析しないのだろうか。今では世の中には今や使える公開データセットがけっこうたくさんあるんだし。こういう状況において、一般的に行われている解析を、大手企業も採用しているということでやらないのはどうかしている。一般的である以上、こちらでもその解析は普通に行うべきである。そういった一般的なことをやった上でやっと「自分たちの強みはどこで使えるのか。」なのではないのだろうか。
今やっていることは「なんか作れたけど、これ誰が要る??」と言っているのと一緒であると思う。はっきり言わせてもらうが、そんな物誰も買わない。なんとなく着実に進捗しているように見えるが、そんなことでは成果を得るまで長期間費やすに決まってる。そんなことでは他社と競争も出来ない。競争しているつもりになっているだけではないか。実際、コンピューターリソース、スクリーニング能力、合成展開の能力など、自分がみたって太刀打ち出来るような尖った利点がなくなっているじゃあないか。ここで5年とか過ごした後に、職務経歴書も対して発展しておらず、給与もそんなに上がっていないのは嫌だ。
もう自分でポジションを上げて、無能な間抜けに良い開発品を見す見す潰させないようにしよう、ということで、そういうことが出来そうな会社に転職することにした。今後はキャリアを発展させると同時に、技術も手堅い物にしていかなければ、55歳になったときに詰むかも知れないと、本気で思っているというところである。