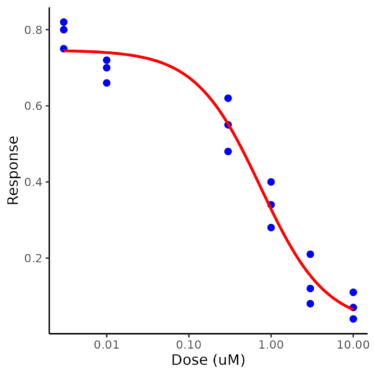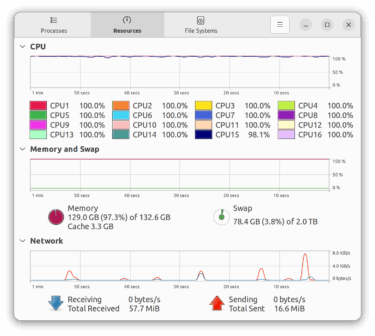日付;2025/08/26(火)
はじめに
創薬ベンチャーで1年半ほど業務をしてきた。そこでは、どんな創薬ベンチャーで履歴書や職務経歴書を発展させることが出来るか、逆に出来ないのかということを自分なりに学ぶことが出来た。それをまとめておく。注意点としては、この記事に記載した内容は自分なりの考え方であり、万人に適用されるものでもないということだ。それでも、ここに書いてあることは、いくらかは正しいことも多いのではないかと考えている。おそらく、就活にもある程度使用できるのではないかと思う。
個人的には、特に創薬系のベンチャーでは、結局のところ業績を得ることを考えた方が良いと思う。アカデミア(大学や研究機関)とは異なり企業では「職務経歴書」を見て面談が進むので、需要が多かったり、流行りだったり、魅力的だったりする仕事内容を職務経歴書に書く必要がある。正直、この職務経歴書はかなり任意性が高い(論文リスト、承認番号付きの認定試験などではない)ので、嘘を言いたい放題な気がするが、しっかりとした手堅い職務経歴書(もちろん、アカデミアで一般的な業績リストも)があれば、ポジションを上げることや給与の増加にも繋がってくる。逆に、これらのような業績を順当に得ることが出来ないような会社は、会社の収益や自分の給与アップを得ることは難しいと思う。「履歴書・職務経歴書を発展させることが出来るか」ということと「会社の収益は上がっているか」ということは、かなり密接に関連している。収益を上げることが出来ない会社は、ずっと同じような業務を行っており、仕事内容、ポジション、等級をそれ以上上げる必要がないために、履歴書・職務経歴書が発展しないためだ。もちろん、収益が出るまでその会社でゆっくりと活動する作戦も考えられるが、それでは次のポジション(おそらく5年くらいかけて号棒を上げてき、それでようやく等級の上昇が検討される。そして等級が1つあがったくらいだと、上のポジションに行けない。)に上がるまでに一生かかってしまうので、自分は好きではない。後述するが、過去に大企業に所属していたとしても、実力を伴った良い履歴書・職務経歴書がなければ転職に対応できないし、日本で給与を上げ続けるためには管理職になる必要があり、転職はそれを短期間で達成するための方法であるが、そのときには明らかに良い業績が必要、すなわち、履歴書・職務経歴書の発展が必要である。
以下に学んだことを述べる。この視点から色々な創薬ベンチャー、特に経過年数、所持しているパイプライン、所持しているプラットフォームなどから、何となくその会社は将来があるのか、無いのかがわかるのではないかと思う。言ってみれば、以下は自分なら今後就職しない創薬ベンチャーである。
会社の情報からわかること
まずは、着目した会社の沿革や、創薬ならば「パイプライン」と呼ばれる、自社や他社との共同研究している開発品の情報は見る価値がある。
ここで、共同研究という言葉を説明する。製薬企業における共同研究とは、アカデミア(大学や研究機関)で使われている共同研究とは少し意味合いが違う。どちらかといえば共同研究ではなく共同開発であり、研究活動はほぼ行わない。それに、それが企業と小さな企業間での共同開発の場合、大企業が出資するために完全に大企業から小企業へのトップダウンの指示での共同開発になり、さらに検討の余地が無くなる印象がある。出資してもらっているから当然であるが、これもなかなかに厄介な場合も有るようだ。
以下、会社の沿革やパイプラインから何となく分かることである。
5年もやっているのに創立当初の開発品に関する成果が無い場合
まず、会社の公式ホームページに載っている情報から知り得ることとして、創業からの経過年数がある。ベンチャーの作法(ISBN; 9784478119372)やスタートアップで働く(ISBN; 9784799329733)という本にも書いてあるが、創薬ベンチャーなのに資金調達が滞っている会社は駄目である。これはすなわち、ベンチャーキャピタルからこれ以上資金をつぎ込む価値はないと判断されている会社である。資金調達のフェーズではない可能性もあるが、その場合は臨床試験に進んでいるか、とか、そういうところを見ればよい。10年も経つのに第1相試験とかでも考え物と思う。これは進捗が遅すぎると思う。なぜこんなに遅いのかといえば、後述のように結局のところリーダーが無能(なんでそんな疾患を対象にした?なんでより高額なことを予想出来なかった?なんでこれまで専門家に聞かんかったの?とか)な証拠と考えることが出来る。自分ならそのような会社には二度と就職しない。また、IND(Investigational New Drug)申請に向けてデータを取っていると言い続けて3年とかいう会社も個人的には駄目である。その理由は、IND申請に使用するデータパッケージは、どう考えてもプロトコール通りであり、そこでつまずいているということは、リーダーが無能なのに加えて、開発品自体が良く無かったり、データに捏造のようなことがあるために上手く行っていないという可能性があると思う。
それに加えて、AMEDのような公的な機関からの研究助成を会社都合で途中で辞めている会社も要注意だと思う。なぜ会社都合で途中で辞めることになったのだろうか。まず、その化合物や開発品に何か重大が欠点がなければ、中止はしないはずだ。その化合物や開発品で会社を立ち上げて、ベンチャーキャピタルを説得し資金を得て、将来的にそれを売り出そうとしている、つまり、会社の運命がかかっているのではないだろうか。それを会社都合で途中で停止させるということは、それをやり遂げるだけの見通し、計画、薬の薬効がない、そういうことを出来ない人間が運営しているということである。会社でやっていることが研究寄りだから許されるでも思ったんだろうか。そういうことで、やはりなにか研究開発を舐めている可能性もある。アカデミアだったら、多少薬効が弱い化合物でもなんとかして終了するはずであり、こんなことは教授やそのコミュニティーは簡単に許してくれない。自分たちは元大企業出身の研究者(ではなく、実際は彼らは技術員の集団である。その理由として、彼ら彼女らは論文を責任を持って書いたことがない。)色々とアカデミアを悪く言う割に、研究開発を舐めているのは自分たちである(自分たちを優秀な研究者だと思っているからタチが悪い)。研究を舐めるなって感じである。ましてやそこは会社なので、こういうところは薬を作るのは無理である。そして、もしそのような開発が続いているならば、過去にその開発に注ぎ込んだ額をなんとか回収しようとして、無駄なのに頑張っている可能性がある。これをサンクコスト(Sunk Cost)という。そして、それが無駄だ、という判断を出来ない会社、そして、そうならないような研究が出来なかった会社ということになる。
こういう会社って今では本当に多いんだと思う。ほんと、無駄に起業しないでほしいと思う。昨今の上場廃止の基準が厳しくなったりした(ゴミが多すぎて2030年からグルース上場の条件が5年で時価総額100億円以上になった。)の背景には、収益が全くないクセに株で資金を得るだけっていう会社が多すぎることもあると思う。
大企業からのカーブアウト
カーブアウトというのは、大企業のとあるプロジェクトに関して、その企業やベンチャーキャピタルから出資を受けて新しく立ち上げたような会社のこと、もしくはその行為のことである。大企業からのカーブアウトと言っている会社もよく考えた方が良い。
このような創薬ベンチャーは、自分の経験上、最も要注意である。自分なら絶対に悪いシナリオを考えてしまう。元は大企業だっただけに様々なノウハウを持っているように見えるが、そんなことはない。考えてみれば、そのプロジェクトは大企業からボツを受けた物の可能性が高いためである。すなわち、元の大企業が将来性や収益が望めないと大企業から捨てられたプロジェクトである。本当に有望なプロジェクトなら、カーブアウトの前にボツにならない。ここで楽観的に考えて、実際のところ有望だったとしよう。それでも要注意、というか、駄目と見なしても差し支えないと考えている。その理由は、元大企業に所属していた各個人にそのプロジェクトを臨床試験まで完遂するまでの能力がない可能性があるためだ。大企業というのは随分と分業が進んでいるようで、ある分野の薬理しか知らん、というのがどうも一般的らしい。これは本当に酷くて、「免疫の部署にいたけど、何とかという細胞株を使ったアッセイしかやったことなくて、安全性や薬物動態は全然知らないんだよね。」ということが本当に起こる。そんな人間に、適切な細胞や組織を使ってリード化合物を最適化し、Target engagementを示した上でin vitroとin vivoでMOA(Mechanism of Action;作用機序)を示し、その薬物動態を得て、安全性試験に回す、という一連のプロセスを考えて出来るわけない。これらは一般的に専門の部署がやるやろ、と考えるべきところであるが、そこはそ創薬ベンチャーであり、2年ごとに出資してもらう必要がある会社である。人集めに1年も2年も費やすことは出来ない。おそらく、何とかして「効率的に」「最小限の人数で」達成する必要があるわけである。
個人の能力と言えば、この「効率的に」というところにも問題がある。彼ら彼女らのうち、まともな研究をしてきた者は極少数である。彼ら彼女らは博士課程はビジネス上の肩書としての価値しかないと考えており、かなり粗末な論文で博士を取っているような、論文博士・社会人博士の連中が圧倒的多数である。彼ら彼女らのすべてとは言えないが、特に修士課程で大学を卒業した製薬企業の連中で、かつ、働きながら論文を出すだけで博士を取得した連中は大体これである。彼ら彼女らはシンプルに無能である。さらに、当然ながら、いい年して修士の人間も多い。そういう奴らは、ほぼ間違いなく、衝動的な実験や思い込みのような実験を行う。成果の形はなんとなく見えているかも知れないが、それはぼんやりと「こんな感じ??」くらいにしか理解出来ていない。彼ら彼女らはゴールを設定し、それに向かって堅牢な計画を立てることが出来ない。成果の形が生半可で見えているのも悪影響しており、そこに向かって都合の良いようにデータを解釈し、挙句の果てはリサーチミスコンダクトのような行為に出る。これがさらに進捗を妨げることになる。間違いなく、サンクコスト一直線である。長年やっているのに次のステージに移っていない企業は、まず間違いなくこれが関係しているように思う。
それに、大企業からのカーブアウトの問題は他にもある。彼ら彼女らは、どうしても大企業の働き方を数人の会社に持ち込む。それもそのはずで、彼らは創薬ベンチャーで働いたことも無ければ、短期間で効率的に次のステージに行くための研究開発も、自分たちでデザインしてやったことがない。知っているのは、これまで大企業でやってきた通りの働き方、すなわち、正式に仕事に割り当てられればその仕事をやる、他のことは他の部署がやる、という仕事っぷりである。2年で次の資金を取り、かつ、次のステージに進めるように自分でデザインして、効率よく、必要なことを自分で行う必要がある。それが頭ではわかっていても、どうやら出来ないようだ。大企業からのカーブアウトは、大企業の残党と考えることが出来る。こういうところは本当に多いので、要注意である。
研究機関発・大学発のスタートアップ
はっきり言って、これは文字通り「ゴミ」である。公式のホームページに書いてある製品やパイプラインを見て「え、これ何につかうん….?」となったら、まず間違いなく投資の価値がないと言える。研究能力は高いのだろうが、肝心の開発品が「ゴミ」なわけである。これはある意味では大企業からのカーブアウトとは別の意味で非常にヤバいのではないかと思う。昨今では日本の国立・私立大学・研究機関の研究能力のレベルはあまりにも低く、世界から明らかに取り残されている。どちらが原因か結果かは何ともわからないが、研究資金も圧倒的に低くなっているように感じる。そして数年前から、大学発のベンチャーなんかもおそらく推奨されりようになってきており、それに伴って実際に企業する研究室などもある。しかしながら、それらのほとんどが圧倒的にゴミを創出している。誰がそんなもの使うのだろうか。それを作ったとして、どんな治療を展開するのだろうか。だれが買うのだろうか。彼らはそれを考えていない。
こうなってしまう原因も何となくわかる。これはおそらく研究室主催者(PI)の業績づくりでやっているだけであり、どれだけ良い品になるかは実際にはほぼ検討されていないためである。そういった研究機関や大学発ベンチャーに就職するのは明確な目標などが無い限り絶対にダメである。だって、考えてみてほしい。本当にその技術を売りたいならば、なぜ自分で売りに出ないんだろうか。それをベンチャーキャピタルやコンサルに丸投げの場合もある。少なくとも、研究能力や業務のスキルが乏しい、もしくは、発展途中の若手がこういう会社に就職してしまうと、研究能力や業務のスキルが乏しいままに時間が経ってしまう。つまり、まず間違いなく時間の無駄、もったいないことになる。逆に、単にそのポジション(上のポジション)や社会経験の既成事実をつくる、という意味では、一般的な給与よりも多くもらったり、いろいろと利点がある場合は、辛うじて有りである。ただし、繰り返すが、何の役に立つかはっきりしない製品に携わるのは、人生の無駄でしかないので要注意である。自分は、これが2030年にグロース上場の基準が時価総額100億円以上に変更になった理由が、こういうところも関係しているんだろうな、と何となく思っている。
アセットが最強かつ医師との連携がある研究機関・大学発のスタートアップ
個人的には、これは条件付きで良いと思う。アセットとは、薬に限らず、要は主力になる商品のことである。まず、とある薬が治療成績を明らかに上げそう、ということがわかるならば随分とマシと思う。しかし、いくらアセットが強くても、医師との密接な連携が無いスタートアップは、BD(Business Development)担当者やリーダーの能力が低い場合は、詰む可能性が非常に高いと思う。逆に、アセットだけでなく医師かなり強力で密接な連携があるスタートアップなら、辛うじて有りということになる。医師との強力なコネクションがあれば、臨床試験のハードルが明らかに低くなる。すなわち、ここで成果を得ることができれば、一気に職務経歴書が充実する。臨床試験へのコネクションやパイプが無いと2、3年の時間制限でアウトになるし、そういったパイプが無い場合、CRO(Contract Research Organization)を使って治験なんかをやると30億円とか普通にかかるらしいので、これらも注意である。ベンチャーはそんなに金持ってない。精々、数億円で結果を出す必要がある。
一方、この手の会社にも注意点がある。アセットが強くても開発の余地がない場合も要注意と思う。例えば「この会社のこの薬、すごく強力でおそらく臨床に出たらかなり良い治療成績が得られるだろうし、臨床の敷居もかなり低いやん….でも、これ開発の余地ある??だってこの会社、ケミストがおらんやん….それに、この製品をどうやって発展させるんだろう….」という状況である。おそらくこういう会社はアセットを拡大するのは無理なんじゃあないかと思う。つまり、その有望そうな薬剤を臨床に出したら、それで終わり、ということである。もちろん、それを使って世界中に展開する、とかは有りそうだけど、それでもそれ以上開発が出来ないというところで大企業が参入してきた時点で間違いなく詰む。
もう一つの注意点として、就職するなら創業間もないスタートアップならばOKということだと思う。これもベンチャーの作法(ISBN; 9784478119372)やスタートアップで働く(ISBN; 9784799329733)という本に書いてあったことでもあり、今は自分でもその通りと思っている。創業間もない会社に、しっかりした基盤を作ることが出来るリーダーとして着任したり、その部下としてしっかりと業績を得ることが出来るようなマネージメントをしてもらうことが出来れば、良い経験が出来て、職務経歴書も充実すると思う。逆に、時間が経つにつれて無能なリーダーが着いてしまい、かつ、資金を得るための業績が、創業後の経過年数に対する資金を得るための業績がなくなっている可能性がある。
個人的には、こういう会社は5年間くらい有限で働き、おいしいところを持っていったらその業績をもって次に進む、という戦略が良いと思う。新しい技術を習得するでも、必要な業績を得るでも、着任の既成事実を得るでも、目的が達成されたら次に転職してしまえば良い。そうすることで、履歴書や職務経歴書を一気に発展させるのが良いのではないだろうか。この方法は他の会社よりも履歴書の発展は早いのではないかと思う。ベンチャーらしいキャリアプランであるとも思う。それに、社長でさえ「この薬を上市したら会社売ろ。」とか考えている可能性も高いと思う。でも、10年居るのは無理かなぁ…。
この手の会社の良い例としてはCART療法とか、そういうヤツである。アセットとしてあまりにも強力、最先端、それ故に魅力的であり、大学や研究機関が開発を手動しており、アセットとしても開発の余地があり、如何せん医師が中心となっているので臨床試験の敷居も圧倒的に低い。こういうところに創業初期から参加できればすごく良いと思う。しかし、こういう会社も、今ではかなり大きくなってしまっており、新しく加入するにはあまり美味しくない(これ以上良い出汁が出ない)ように思う。そのような状況で、どんなスキルを得ることが出来るだろうか。どう考えても、ほしいスキルが手に入り、履歴書や職務経歴書が出来上がってきたら(味を理解して自分でもそれを作れるようになったら)、次の会社で良いポジションと高い給与を狙うべきである。
プラットフォーム事業を謳う企業
よく見る会社の形のひとつと思う。こういうところは、今あるものでまずは収益を得る必要があり、十分な開発の時間がない、というベンチャーの性質により結果として研究開発が制限され、そして、最終的に詰む未来が見える。
例えば「3000種類くらいの化合物を持っていて、それをプラットフォームとして利用することで、どんなタンパク質、遺伝子でも標的に出来ます」という形態である。こんなもん大企業が参画したら一発で駆逐される。数でいうと、大企業やノウハウがある会社では、合計Trillionの化合物をスクリーニング出来ます、とかになる。もう桁が違う。3000化合物って….
上述のように、ベンチャーは先ずはそのプラットフォームの実績や創薬におけるFeasibilityを示す必要があり、その一方、プラットフォームの開発に費やす時間や金が十分ではないと思う。創薬ベンチャーなので小規模少人数であり、将来的に有望なものをさらに開発していくまでの余裕もない。研究リソース(人材、時間、金、機材、コンピューター)を常に拡大しなければならないのに、それが難しいという状況が絶対に起こる。 こうなってくると、どこかに買収されて終わりである(社長はこれを狙っている可能性は大いにあるのだが….ここで犠牲になるのは部下である。)。ビジネスしなくちゃいけないのに、研究開発も並行しなければならないという状態になり、結局共倒れし、CROも含めた大企業やノウハウのある企業から大幅に追い抜かれてるか、たたき売りに出されるか、と思う。
面談からわかること
とはいえ、面白そうな会社や、自分の専門分野と被っていそうな会社と思っても、どうしようもない人間がいたりもする。こういう奴は面談から判断できれば良いのだが、これは本当に難しい。大企業で長年生きて来ることが出来た奴は、人当たりも良く、正確も良く見え、なんだかんだで喋りが上手だったりするので、まず間違いなく都合の良いことを並べて、煙に巻こうとしてくる。なので、自分がこれまでに得てきた知識や経験から、なんとかして煙を除いて、できる限り本当のところを見破る必要がある。しかし、やはり相手は口上がうまいので、難しいとは思う。それに、企業であるから、発表ではチャンピオンデータしか出してこない。ここもなかなか難しいところである。
発表での質疑応答のクオリティーが低い。
これはインダストリー(企業)もアカデミア(公的な研究機関・大学)でも同じことである。折角これまでの職務や研究内容についてスライドを使って発表しているのに、まるで興味が無いかのように何の質問も無かったり、あっても明らかに的を外していたりした場合である。この場合、その求職者に興味はないと考えて良い。また、こういう連中は、発表内容ではなく、この会社の業務に関する内容に、一瞬にして話を移す。こういう連中が求めている物は、単に作業をこなしてくれる技術員であり、なにかを生み出してくれるような研究員ではない。そして、こちらのキャリアに関しては全く考えてくれない。それに、こういう人間は他人の理解、社会の要望に答えること、全体を俯瞰することなどが下手であり、アカデミアでもインダストリーでも、リーダーとしては無能といえる。アカデミアなら、同じ実験をまるで趣味のように一生繰り返すことになるし、インダストリーなら、上手に退却出来ないので、サンクコストを量産する羽目になる。おそらく、何か作っている事自体が目的になっている。
リーダーが高齢。
面談で、リーダーが明らかに高齢であった場合は要注意である。高齢の問題点は沢山ある。後述するリーダーの能力にも密接に関係していると考えられる。面談などの表面的な会話から判断するのは難しいが、再雇用なのにリーダーのポジションに付いているような人間、そのようなマネージメントをする会社は、駄目である。そういった人は人間的、性格的にはとても良く、だからこそ好かれているのかも知れないが、業績を出さないと火の車になるような場合や期限付きの場合など、どっちにしても老害である。実際の能力の低さとかなり相関していると思う。以下が高齢者の要注意点である。
ちなみに、自分が思う再雇用で最も効果を発揮するのは市役所の職員のような、規則に従って業務を遂行するような場合で、そういった業務の経験値がモノを言う場合だろうと思う。一方、研究や開発のように、常にトラブルを解決したり、新しいことを生み出したり、新しいことを試しながらも効率が必要だったりする場合は、色々と問題が出てくるような気がする。どうしても高齢だと以下に記載する特徴が影響するように思う。
1.体力がない。
まず、体力がない。上述の通り、創薬ベンチャーでは、少人数にも関わらず2年ごとに開発を発展させ、資金を得て次の段階に進み、更に開発、ということを繰り返す必要がある。2年で成果を出そうとすると、随分と精力的に開発を進める必要がある。高齢だとそこに付いてこれない。例えば、対象とする開発品は特定の免疫細胞に作用する化合物だったらどうだろうか。業者から標的細胞が購入できれば良いが、もしそれが出来なかったら、組織からそれらを単離し、次にex vivoでアッセイすることが必要である。セルソーターを使っている場合でも、回収できる細胞数によってはかなりの時間を使うことになり、実験は普通に夜中になる。経験上、このような実験の日は、終わるまでに12時間は最低でも使う。その時間経過を追う必要がある場合、そこから4時間後、8時間、12時間後である。後述するが、こんな実験を一人でやることは効率が悪く、リスキーであり、社会人のすることではないので、チームワークも必要である。彼ら彼女らにこんな作業をする体力もそのようなマネージメントをする能力もない。大学病院で臨床検体を待つ場合でも、遅い時間になる確率がかなり高い。そのような実験に耐える体力も気力もない。
2.腰が重い。
必要だけど知らないことうや新しいことに対する抵抗が大きすぎる。これは、しっかりとした論文を自分が主導して書いていればそんなことは無いようだが、中途半端な企業から来た者だったり、最終学歴が修士で、大企業出身の者だったりするとこれに当たる確率は高いように思う。ゴールを常に頭に置くことが出来ない人、その達成のために必要なデータを考えることが出来ない人に腰の重さが加わったら最悪である。問題を解決するためにはどうしてもこれまでに経験がない実験や手技を試す必要があるが、こういう人はどうやってもそれを避ける方法を取ってしまうようだ。また、部下にその手法を試させるのは良いとして、その実験自体を理解しようとしなくなり、何が失敗していて何が成功なのかさええ考えるのを止めるらしい。データを得たとしても、それをゴールに合うように都合良く解釈してミスリードし、後々に取り返しのつかない事態になる。CROのマネージメントにも最終的に頭を使わなくなる。面倒なのか、CROに仕事の丸投げを始めてしまう。丸投げとコントロールは全然違う。これは、CROをマネージメントしているとは言えないような状況になり、結果としてミスリードしてしまう。
3.責任感が無い。
同時に、高齢になると責任感も減少するようだ。自分はもうすぐリタイアすると考えているので、例えば、自分があと2年会社が持てば良いと考えているのだと思う。だから、問題を解決するのではなく、その問題に蓋をして、そこを回避することで問題を避けて仕事をするようになる。デキるCEOなどはやはりそのリーダーを信用して仕事を任せていたりするので、そうなってくると、そのプロジェクトは後戻り出来ないところまで行ってしまう。
回避に加えて、無駄に仕事を長らえさせる、ということも起こり得る。要するに、彼らは後2年くらい会社に居ることができれば良く、プロジェクトの成功や失敗は関係ないと考える。その結果、問題解決にはならないが、自分が行うことが出来る、楽な実験を良いデータが出るまで延々と続ける、ということを行い出す。そして良いデータが出たら、それを採用して次に進む。これは再現性があまりにも乏しく、後にプロジェクトは確実に失敗する。
リーダーの能力が不十分。
高齢であったとしても、過去に様々な研究成果を残したり、様々なプロジェクトを成功させたりした人、つまり、能力が十分に高い人であれば、上記のような失敗は少ない可能性はある。しかし、年齢が若くてもあまりにも知識や経験不足な場合は、似たような結果になってしまう。高齢になってくると、能力が無いことと、上記のような高齢によるリミテーションが二重に起こるのでタチが悪い。
結局、サイエンスもビジネスも目標を達成するための手段であり、出てきた結果には原因があるという原理は同じである。リーダーにこそ、これが必要であると自分は考えている。
これは高齢であることと大部分が被ってくる。年齢と能力は独立していると考えているが、高齢になってきてパフォーマンスが低下してくると、能力だって当然に低下していくる。
1.データを解釈できない。
なぜリーダーを張っているのか疑問である。例えば、ある化合物が、ホスト(ヒト)の免疫細胞Aを抑制することで、がん免疫を活性化させ、腫瘍の増殖を抑制する、と想定されて開発されていた、としよう。しかし、様々な解析により、どうやらこの化合物は免疫細胞Bを活性化することで、がん免疫を活性化させ、腫瘍の増殖を抑制していた、ということがわかったとする。そして、過去のデータを見直してみて、当初の想定が外れていたから、こんなに実験がうまく行っていなかったと示唆されたとしよう。普通ならば、では、使用する細胞種を変更し、3種類くらい作ってそれを検証しようか、となる。しかし、彼ら彼女らはそうならない。「いや、これは免疫細胞Aであるべきなので、もう一回実験します。」となる。もう一回実験する、とか、そういうことでは無い。しかし、どうやら本気でわからないようだ。
上記の例を見ていると、能力が足りていないことが良くわかる。まずはスクリーニングに使う細胞である。がん免疫の場合、モデル細胞ではなく、本物のヒトの免疫細胞、具体的にはPBMCを使用しなくてはならないはずなのに、便利だからといって、白血病細胞株を使ってリード最適化を完了させてしまい、実際のPBMCで検証したら全く効果がなかった、ということになる。最初にゴールを考えたときにこれに気が付かないといけない。仮説の間違いに気づいて、正しく戻ることが可能ならば、当然、そうすべきである。戻ることが出来ないとわかっているならば、なおさら良く考えて計画を立てるべきである。なのに、後戻り出来ないところまで来てしまう。
2.問題解決できない。
こういうヒトが良く言うことは「あの大企業に居たときはそうやっていた」とか「いつも30 mg/kgで投与してきたからそれでいい。」とか、そういうことである。対象となる疾患や細胞、標的、化合物がことなるのに、それでも変えようとしない。思考停止状態に成ってしまっているらしい。
上述の続きであるが、免疫細胞Aの抑制を想定していたが、実際には明らかに免疫細胞Bの活性化であった場合など、もはや解析方法が全然違ったりする。それなのに、その解析方法を採用しない。どうやら、彼ら彼女らからしたらその実験は現実的では無いらしい。でも、それをやらなければ失敗する。
でも、そうやって5年も8年も間違った解釈、手法で開発を進めた結果、そのプロジェクトは失敗し、会社としてはなんとかその費用を回収しようとし、後戻りできない状態で無理やり解決しようとする。企業イキり用語でMitigationという言葉で表現されるが、そもそも、Mitigationだってゴールを達成するための代価案なはずであり、このような「言い訳」や「抜け道」ではない。言い訳や抜け道にもなってないしな。
そして、データから見ておそらく最適であろう実験が、自分の全く知らない、やったことがない物であった場合、その実験は行わずに、これまで無駄に行ってきた実験から、「効果がない」として、その現象の検証を止めてしまう。
3.判断できない。
これもうんざりすることである。リーダーなのに、重要な決定をすることが出来ない。企業的に言えば、企業イキり用語を使うなら、Decisionする能力がない。これも上記の問題からの続きである。データの解釈が出来ないから、その問題を解決できる方法がわからないので、まるで逃げるような計画を立て、その逃げるような計画を実行してよいかどうか(当然、駄目であるため)、自分ひとりでは判断できないから、部長・部門長クラスの人に判断してもらうのである。こうなってくると、こいつは必要ない。もう中間管理職でもない。
4.マネージメント能力が低い。
そして、データの解釈も、問題も捉えることも、それを解決するための案も思いつかず、自分の経験がないからその解析を行う必要があることも認めず、そのデータを取ることを中止してしまう。このように、必要なこともわからないということは、当然、その実現のための計画を練ることも考えることが出来ない。この結果の一つとして、チームに具体的な指示や相談をすることも出来ない事がある。また、それが外部のCROでやってくれるとわかった瞬間、それを丸投げ外注する。その結果、数百万円を平気でドブに捨ててしまう。これは想像なのだが、CROに対して打診するとき、おそらく「この化合物でこの実験してこのデータだして。出来る?」ということか言っていないのではないかと思う。この問題も結局のところ、個々の能力の低さに関連している。必要なデータがわからないし、そのデータの取り方も起こり得る問題点もしらないためである。
これに関連して、こういう人たちは「チームを使う」ということも習得していない。話は脱線するが、以前の職場でXXな技術員から「技術員を使う」というフレーズことを「自分はモノではないのでそういう言い方をするな」と言われて、大喧嘩したことがある。ここに来て、結果的にそれは間違っていると確信している。強いて自分の間違いを正すとすれば、技術員は正しく使わかなければならない、ということだ。「技術員を使う」ということは本質的には全く間違いではない。使う者の能力が無いと、全員が不幸になるということである。技術員レベルの能力の人間に問題を解決したり、モノを形にしたりする能力はない。訓練されていないのだから。技術員も自分たちを使われることに対して無駄な抵抗をしないでほしい。お前らレベルだと、結局なにも達成できやしない。こちらとしては「正しく」使う、ということが重要である。言いたいことは、大変な実験でも、チームで全員でかかれば、その問題は解決出来ると思っている。それが大変なのはわかるが、それでも解決しなければならない場合は、やる必要がある。いい歳に成ってくると体力が落ちていくるのは当たり前である。だから、こういったチームのマネージメントも必要になる。逆にこちらは良く勉強して、それを達成できる能力を備えなくてはならない。
当然、部下に不機嫌を巻き散らかす、とかは不味い奴だと思う。
企業と研究機関のポジションの差を理解して就活すること
インダストリー(企業)で使われている用語の意味がアカデミア(大学・研究機関)と違う。タチのが悪いのは、インダストリーの人間も、その用語はアカデミアと同じと思っているところである。用語の真意をわかっていれば、ベンチャーへの就職もわりかし成功するのでは無いかと思う。
企業での「研究員」は研究機関での「技術員」。
企業の募集で、研究員とか書かれていることをよく見る。特に良く知られた企業であれば、給与もかなり良いので、研究機関に長らく居た者は、企業での研究員をそのまま研究機関での研究員として解釈してしまう。しかし、これは多くが間違いと思う。企業で研究員というのは、すなわち技術員である。これは企業という性質を考えてみれば腑に落ちる。本当に大きな企業であれば、この限りではないようだが、数百人規模の企業やベンチャーでは、こういうところは多いと思う。
企業はその性質上、多くのプロジェクトには既に決まった目標、推定されるMOA、標的となっている疾患やそれに関連する細胞やモデル動物があり、それを使って必要なデータを出していく仕事が多いと思う。つまり、その大本のプロジェクトを決めるポジションにでも居ない限り、作業は技術員になる。ここを勘違いすると、かなりキツいことになる。
一方で、企業からはそれこそ研究員のような仕事ぶりが期待されており、それが公言されていたりする。これが上述の「インダストリーの人間も、その用語はアカデミアと同じと思っている」というところである。しかし、ここもやはり企業の性質上、研究的なことは無理があるので、技術員的な作業をやったとしよう。そうすると、お前は研究員だから、もうちょっと高レベルのことをしないといけない、となる。そして、じゃあ、高度なことをするか、といって本気を出したら、今度は誰も付いてこれなくなって、結局レベルを最適化する羽目になり、技術員的な作業になるということが起こる。
会社ごとに文化や開発の進め方や考え方が違うので、この限りではないかも知れない。
企業での「チームリーダー、PI」は研究機関での「研究員」。
企業で多少なりとも考えることが出来るのは、チームリーダー、上席研究員、PI(Principal Investigator)とか、そういうポジションである。しかし、これも研究機関とも少し違う。研究機関でチームリーダーとかPIと行ったら、ラボのトップとか、そういう感じであるが、明らかにそこまでの権限がないように見える。すなわち、このプロジェクトをやるから率いてください、という感じになり、すなわちこれは研究機関での「研究員」のポジションに当たる。チームを持つことが出来るので、そのチームを運用して目標を達成する、というのは、やりがいはある。一方で、研究機関ほどの自由は期待できない、というか全く無いので注意である。
そして、ここからは想定なのだが、それこそ研究機関における「チームリーダー、PI」とかのレベルは、企業ではその上のマネージャーやディレクター的なポジションになる。これはよっぽど難しいポジションになると考えられる。
自分なりのベンチャーの選び方
以降は、ここ1年半で色々と観察して学んだ、自分なりのベンチャーの見極め方である。自分の解釈なので、万人に当てはまるとは限らないので注意が必要である。
口コミは案外正しい
いろいろな転職サイトを見ていると、特に少し長い期間運営している会社に対しては口コミが挙がってくる。それは、案外正しいので、信じる価値があると思っている。
その口コミは会社全体の様子を表してはいないだろうし、もしかしたらその人に原因があった可能性もあるが、少なくともその人はそのように感じたり、そのような待遇だったことを示す。また、たまに「完全にトップダウンであり、開発や研究の余地が残されていない。」というコメントがある。このコメントは、おそらく、その会社が主眼をおいている分野、例えば化合物のプラットフォームを謳う企業であれば、ケミストの意見しか検討してもらえず、応用に必要なのは実際の生物医学研究だったりするのにそちらの意見はほぼ参考にされない、それでいて、応用が発展しているように見えない、という状況があると考えることも出来る。よって、その口コミは部分的に正しいと言える。他には、「外からしか管理職を採用せず、ポジションがほぼ上がらない。」なども、それに対してなんでやねんと思っている人がいるということである。そういうところは、おそらく技術員しか求めて居ないのかも知れない。口コミのような情報から想像できることと、Job Descriptionに書いてあることに矛盾を感じたら、面談のときに間接的な質問になってしまうと思うが、そこはしっかり聞いた方が良い。
本当に治療に使えるのか
分解薬、核酸医薬、iPS、AI関係…すでに全部二番煎じである。創薬ベンチャーでは大いに有り得ると思う。今からこんなのをやろうとしたって、遅すぎる。もう既に大企業が参入しているような分野では、勝てないと思う。また、作用機序でも標的でも、既存の薬に毛が生えた程度であれば、それは既存の薬に利点がある。臨床試験も進んでるし、どう考えてもリスクを取って二番煎じに投資するのは微妙である。会社のホームページに、ポリシーとして患者のことを考えてるとかが書いてあったら、それは嘘である。社長の趣味なので、そんな奴に付き合ってやる必要はない。もし何かよほどの利点があって入社するにしたって、その目的をさっさと達成し、自分の履歴書を良いものにして、とっとと次のポジションに挑戦して、さらに履歴書を発展させ、ポジションと給与アップを狙ったら良いと思う。ある程度論文を書き、助成金を実力でもぎ取ってきた研究者ならその判断だって出来ると思っている。
ある程度のポジションに来てしまった場合、やはり、実績が問われてくる。そこでは、これまでのようにあるスキルを得るために研究員になる、というキャリアが、能力的にも年齢的にも合わなくなってくる。その場合、管理職としての実績が必要になるわけだが、その目的のために、上記のような二番煎じ事業会社に就職するのはどうかと思う。その理由は、それが実績になるためには、二番煎じだけに、解決すべき問題がかなり大変になり、それだけに相当な時間もかかってしまうことになる。
それがベンチャーなら尚更で、そこで二番煎じの開発品に手を出したら、そのコストや時間に耐えるだけのキャパシティーなんか無いわけだだから、必要な実績を得るのが困難になる。
どうせベンチャーなのだから、自分の知識を総動員して、その開発品が、本当に重箱のすみをつついたような化合物や作用機序ではないか、本当に治療成績を上げるのか、大企業が追従してくるのか、ということを全力で想像する必要がある。
臨床試験までの道筋が見えるか
自分のポジションを効率的に上げたり、イカつい履歴書に発展させたりするためには、これはもしかしたら決定的と思う。それに、最終的に臨床試験まで行けない会社は、先がなく、良くてM&Aである。上述したが、M&Aで利益があるのは社長や経営陣だけであり、その他の社員にはデメリットの方が明らかに多い。
経験も無いのに臨床試験まで行くのはかなり大変である。知識も必要だし、膨大な資金も必要である。しかし、もし完全に医師達がバックに付いていたらどうだろうか。臨床試験まで行くためのリクエストをすぐに取ってこれるし、如何せん医師自身がその知識を持っているため、その敷居は格段に低い。
それに、医師は効きそうもない薬なんて、以下に作用機序が新しくても見向きもしない。一方、そもそも臨床でバリバリやっているような医師であれば、かなり有望な薬を開発している可能性もある。そういった会社を選ぶべきと思う。つまり、「アセットが最強かつ医師との連携がある研究機関・大学発のスタートアップ」がベンチャーとしては一番良いのではないかと思う。
自分にとって必要なキャリアを築けるか
ベンチャーで働いてみて度々考えることは、これから自分のキャリアをどうやって発展していこうか、ということである。自分は30代までは、その分野ならどんな研究も出来るし、効率的に目的を達成できるように能力を高めてきた。しかし最近、このような方法では、チーム内での関係性、能力自体、今後給与を上げるためのポジションなどと整合性が取れなくなってきた。すなわち、チーム内では自分だけ研究能力は明らかに突出しているし、だからといって明確なチームも持っていない中途半端なポジションなので、勝手に動くことは出来ない。なので周囲に問題解決の方法だけを伝えるけど、そんなことを到底周りが理解できないし実行も出来ない。これ以上改善したり発展させるためには、管理職になるしかないように思っている。それに、そうしなければ目的のプロジェクトや目的を達成したり、給与を効率的に上げたり出来ないようにも感じている。
ベンチャーは大企業に比べて人材も資金も少なく、それにも関わらず、こういったところでボヤボヤしているほどの時間もない。長い時間居たら、良くも(M&A)悪くも(倒産)会社がなくなってしまう。一番良さそうなのはIPO(Initial Public Offering; 新規公開株式; 新規上場)であるが、それにしたって大企業が同じ分野に参入してきたら同じことである。
なので、ベンチャーでの働き方、格好の良い言い方をすれば、ベンチャーを使ったキャリアの発展のさせ方、悪い言い方をすれば、ベンチャーを使った給与の上げ方は、最初に明確なゴールを設定し、そのゴールを短期間で達成できる会社を見極め、そのゴールに達したら、会社の内外を問わず、次のポジションに挑戦し、さらにキャリアを発展させる、給与を上げるように働きかける、転職する、という作戦で活動する必要があると気がついた。
それを指示することとして、ベンチャーの社長もおそらくこの会社で10年活動する、なんて考えていないのではないだろうか。おそらく、続けること(IPO)と売り払うこと(M&A)の両睨みで運営しているはずである。だから、こちらも、忠誠心でキャリアを考えていたら駄目であるとわかった。ゴールに達したら次を考える。それが一番良い気がする。明らかに2、3年区切りで自分の履歴書を発展させる必要がある。それが出来ないなら、そんな会社は遅から早かれ消滅するのでは無いかと思う。
まとめ
いろいろと書いてきたが、ベンチャーで働く理由なんか、結局のところ、一番最後に書いた「自分にとって一番価値のあるキャリアで、能力に応じた金をしっかりと稼げるのか」というところに帰結するのではないかと思う。どういう創薬ベンチャーに行けば、自分のこれまでの経験や能力を活用でき、上手いこと非臨床試験から第三相試験までたどり着いて、イカつい履歴書を仕立て上げることができるのかを考えれば良いと思う。これを考えれば、自ずと「この会社のアセット本気かよ…」とか、「化合物3000くらいでプラットフォームかよ…」とか「この化合物イケそうだな….」とか「これ、どうやって臨床試験するんだろうか….」とか「ここ、明らかにケミストの趣味だな….」そういうこともなんかわかってくる。